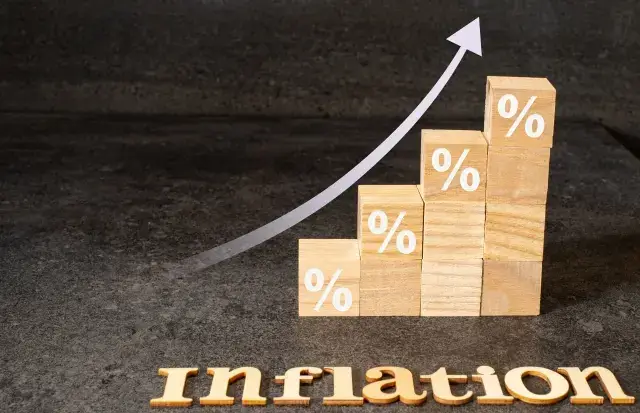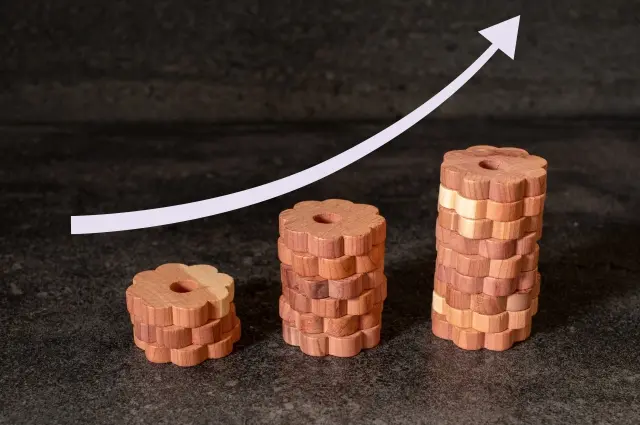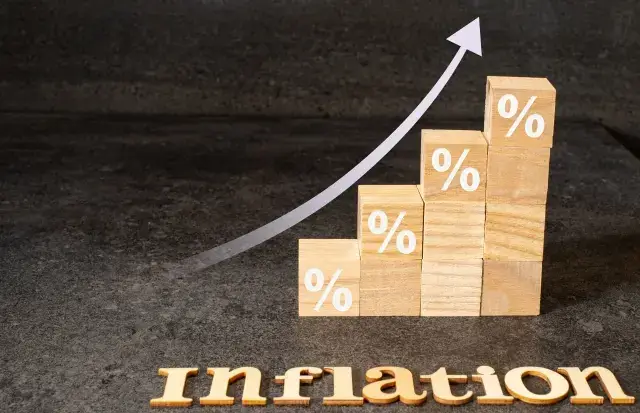 (※本記事は2025年3月28日作成、2025年12月12日更新)
(※本記事は2025年3月28日作成、2025年12月12日更新)
近年、物価の上昇を肌で感じる機会が増えていませんか?スーパーやコンビニでの買い物、ガソリン代、家賃——あらゆるものの値段が上がる一方で、給料は思うように増えない。これはまさに「インフレ」の影響です。
インフレが進行すると、お金の価値は目減りし、同じ金額で買えるものが少なくなります。日本でも、食品やエネルギー価格の高騰が続き、実生活への影響が無視できない状況になっています。
では、そもそもインフレとは何なのか?なぜ日本でもインフレが進んでいるのか?前編では、インフレの基本的な仕組みと、日本におけるインフレの現状について詳しく解説します。

向井 啓和 不動産投資アドバイザー
1999年から不動産投資をメインに、アメリカ不動産投資、アメリカドル投資、日本株投資を行ってきた投資経験を元に、長期投資で成功するためのヒントを共有します。
この記事の概要
物価高騰を肌で感じる今、現金の価値が目減りする「インフレ」の仕組みと現状を解説。インフレが生活に与える影響(実質賃金の低下、貯蓄価値の減少など)を理解し、「良いインフレ」と「悪いインフレ」の違いを明確にします。日本が直面するインフレ要因と、資産を守るための意識改革を促す基礎編です。
目次
- 1.インフレに対する理解とは?
お金の価値が目減りするインフレの影響 - 2.良いインフレと悪いインフレがある?
良いインフレとは?
悪いインフレとは? - 3.日本におけるインフレの現状とは?
日本のインフレ要因 - 4.日本のインフレの方向性
- 5.インフレ時代にどう備えるか?
インフレ下のお金の価値の変化
1.インフレに対する理解とは?
インフレとは、物価が継続的に上昇し、相対的にお金の価値が下がる現象を指します。インフレが進行すると、同じ金額で買えるものが少なくなり、現金を持っているだけでは実質的に資産が目減りしてしまいます。
日本でも、近年インフレ傾向が見られ、食品やエネルギー価格の上昇を実感している人も多いでしょう。そのため、インフレの影響を正しく理解し、適切な資産運用を行うことが重要になります。
お金の価値が目減りするインフレの影響
インフレの影響は、私たちの生活に直接的な負担をもたらします。最近では、食品価格の上昇が顕著で、例えば以前は3,000円で5キロの米が買えたのに、今では同じ金額で2キロしか買えないといったケースもあります。

これは、物価が上昇することで、お金の価値が相対的に下がることを意味します。以下のような影響が考えられます。
<インフレの主な影響>
✔実質賃金の低下 – 物価が上がっても給料が追いつかなければ、生活が苦しくなる
✔貯蓄価値の減少 – 現金を銀行に預けているだけでは実質的に資産が減ってしまう
✔生活費の増加 – 食費や光熱費、家賃などの固定費が上昇し、家計が圧迫される
✔企業のコスト増 – 材料費や人件費の上昇により、原価の上昇が続く
特に、年金生活者や低所得者層はインフレの影響を強く受けやすいため、将来の生活を守るための対策が必要です。
2.良いインフレと悪いインフレがある?
インフレというと、「物価が上がって生活が苦しくなる」というネガティブなイメージを持つ人が多いかもしれません。しかし、インフレには『良いインフレ』と『悪いインフレ』の2種類があることをご存じでしょうか?
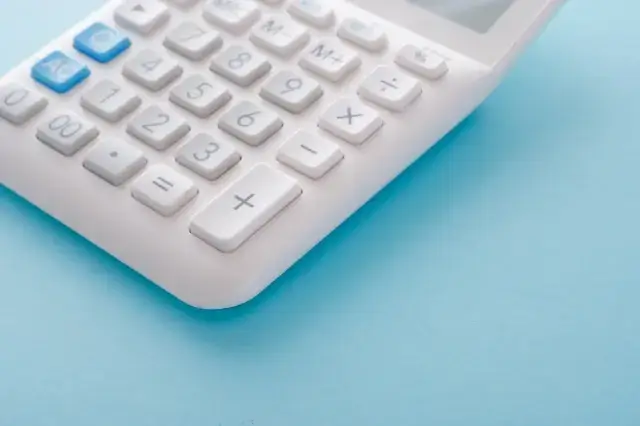
✔ 良いインフレとは?
「良いインフレ」とは、経済成長とともに物価が緩やかに上昇する状態を指します。たとえば、企業の業績が向上し、それに伴って給料も上がるような状況では、多少の物価上昇があっても生活は苦しくなりません。
このような健全なインフレが起こると、次のようなメリットがあります。
企業の利益が増える → 賃金が上昇し、消費が活発になる
経済全体の成長につながる
適度なインフレがあることで、企業や個人が投資をしやすくなる
政府や中央銀行(日本では日銀)は、経済を適度なインフレ状態に保つことを目標としています。
✔ 悪いインフレとは?
一方で、「悪いインフレ」とは、物価が急激に上がるのに対して、賃金の上昇が追いつかない状態を指します。こうなると、生活費がどんどん増え、家計の負担が大きくなってしまいます。
特に、以下のような状況が発生すると「悪いインフレ」となります。
エネルギー価格や原材料費の高騰により、企業が価格を引き上げざるを得ない
(コストプッシュ型インフレ)特に、現在は円安の影響で原材料の輸入物価の上昇が大きな問題となっている。
貨幣の供給量が増えすぎて、通貨の価値が下がる(ハイパーインフレ)
給料が上がらないのに、食料や生活必需品の価格が上昇する
最近の日本のインフレは、「悪いインフレ」に近い状態と言えます。企業が仕入れコストの上昇を価格に転嫁し、食品や日用品の値段が急激に上がる一方で、給料の伸びはそれほどではないためです。
3.日本におけるインフレの現状とは?
日本では、近年インフレが緩やかに進行しています。以前は長期間にわたるデフレが続いていましたが、ここ数年で物価上昇を実感する機会が増えてきました。

その背景には、世界的な資源価格の高騰や円安の進行、そして国内需要の回復の遅れといった複数の要因が絡み合っています。さらに、世界の主要国の経済政策がインフレを助長する方向に動いていることも、日本の物価上昇に影響を与えています。
日本のインフレ要因
✔ 輸入物価の上昇 – 原材料やエネルギーを海外から輸入しているため、価格が上がると物価に直接影響する
✔ 円安の影響 – 円の価値が下がることで、輸入品の価格がさらに上昇
✔ 資源価格の高騰 – 原油や小麦などの価格が世界的に上昇し、生活必需品の値段が上がる
✔ 需要の回復の遅れ – 経済回復が遅れることで、企業の価格転嫁や賃上げが十分に進まない
✔ 世界的なインフレ傾向 – 各国の財政政策や地政学的リスクが、日本の物価にも影響を与える
世界の経済情勢とインフレの影響
現在、世界の主要国は財政拡張政策を進めており、これがインフレを加速させる要因となっています。
アメリカ:トランプ政権では関税を引き上げる方針を示しており、物価上昇を引き起こしやすい状況にあります。関税が上がることで輸入品の価格が高騰し、企業はコスト増を消費者に転嫁せざるを得なくなるため、インフレ圧力が高まる可能性があります。
ドイツ:債務上限を撤廃し、国債を発行して財政支出を拡大。国防やインフラ投資を増やす方向に進んでおり、これはインフレ要因のひとつとなります。
ヨーロッパ各国:ロシア情勢やアメリカの政策の影響を受け、防衛費を増加させる動きが広がっています。防衛支出の拡大は財政拡張を促し、インフレを加速させる可能性があります。
中国:景気悪化への対策として、超長期国債を発行し、財政拡張政策を進めています。これにより経済成長を促す狙いがありますが、インフレリスクも伴います。
経済規模の大きい主要国が軒並み財政拡張路線を取っているため、世界全体のインフレ圧力が高まりつつあるのが現状です。
4.日本のインフレの方向性
日本は依然として低金利政策を維持しており、日銀の政策金利は0.5%と非常に低い水準にあります。確かに金利は上昇基調にありますが、それでも世界と比べると依然として低水準のままです。このため、日本は引き続き円安が進みやすく、輸入物価の上昇を通じてインフレ圧力が高まると考えられます。
ここ数年の傾向を考慮すると、日本のインフレは今後も継続する可能性が高いでしょう。円安が続くことで輸入コストが上がり、生活必需品の値段はさらに上昇する可能性があります。
5.インフレ時代にどう備えるか?

インフレ下のお金の価値の変化
日銀のインフレ目標は2%とよく言われますが、これがどういう意味を持つのかを単純な式で示すと、以下のようになります。
<インフレが資産価値に与える影響>
① 10,000円 – 10,000円 × 2% × 5年 = 9,000円
(分かりやすく単利で計算していますが、実際は複利で考えるため、さらに価値が低下します。)
📉
② 10,000円 – 10,000円 × 2% × 10年 = 8,000円
(同様に、実際の計算ではさらに価値が減少します。)
📉 今日の1万円の購買力は、10年後には8,000円相当になる
つまり、現金をそのまま放置すると、実質的な価値が目減りするということです。タンス預金や普通預金では、お金の価値が下がるのを防ぐことはできません。
このような環境では、現金を持ち続けるだけでは資産の価値が目減りしてしまいます。では、どうしたらよいのでしょうか。
次の記事では、インフレに強い資産や投資方法について詳しく解説します。