 (※本記事は2025年12月17日作成)
(※本記事は2025年12月17日作成)
都心マンションの価格高騰に伴い、投資目的で購入したマンションを完成前に転売する動きが目立っています。
特に晴海フラッグでは法人・業者による大量取得と短期転売が問題視されており、業界団体は「引き渡し前転売禁止」の方針を打ち出しました。
本記事では、晴海フラッグの事例を交えながら、転売規制が投資戦略に与える影響や今後の不動産投資のポイントを解説します。

向井 啓和 不動産投資アドバイザー
1999年から不動産投資をメインに、アメリカ不動産投資、アメリカドル投資、日本株投資を行ってきた投資経験を元に、長期投資で成功するためのヒントを共有します。
この記事の概要
東京都心のマンション市場で進む短期転売の問題を背景に、業界団体が「引き渡し前転売禁止」の方針を提示。晴海フラッグでは法人や投資会社による大量購入と高値転売が実際に起きています。本記事では、この事例をもとに、転売規制が投資家に与える影響、長期保有・賃貸運用の重要性、契約時に押さえるべきポイントなど、都心マンション投資の今後の戦略を分かりやすく解説。
目次
- 1.都心マンションの転売が問題となった背景
- 2.晴海フラッグで実際に何が起きていたのか
- 3.なぜ「引き渡し前転売禁止」が重要なのか
- 4.投資家が受ける影響とリスクの変化
- 5.投資家が今押さえるべきポイント
- 6.まとめ:長期保有時代の本格到来
1.都心マンションの転売が問題となった背景
都心部のマンション価格は、数年前から外国人投資家の資金流入や金利の低さを背景にじわじわ上昇していました。
ある時期から、「買うのは簡単だけれど、住むつもりはない」という買い手が増え、短期で売り抜ける“フリップ(転売)”が見えやすくなりました。
とくに湾岸エリアは、供給量やブランド性、「大型供給の話題性」などが重なり、転売による価格上昇が目立ちました。
その結果、
- 実需の買い手が購入しにくい
- 価格が安定しない
- 市場が投機的になる
このような問題が徐々に表面化して参りました。
2. 晴海フラッグで実際に何が起きていたのか
 晴海フラッグは、もともと大規模な街づくりを目的として販売された物件です。
晴海フラッグは、もともと大規模な街づくりを目的として販売された物件です。
しかし実際には、法人による大量取得や投資用のまとめ買いがありました。
全1089戸のうち 292戸が法人名義
業者が1社で30戸以上購入したケースも存在 発売時より 2倍近い価格で転売された住戸もある 実際に取材記事や業界内の話を見ていると、「あれほど法人が多いマンションは珍しい」という声もありました。
この状況を受けて、デベロッパー側は購入数の制限や社名チェックなど、転売防止策を徐々に強化することに。
背景と今回の方針
東京都心、とりわけ湾岸エリアのマンション相場が過熱しており、短期転売(フリップ目的)で大量に取得する投資家や法人の存在が指摘されています。
この流れを受け、不動産業界団体による「マンション引き渡し前の転売禁止」という方針が浮上しました。
この方針は、投機マネーを抑制し、
実需層や長期保有・賃貸運用を前提とした住宅市場を守る狙い
があります。
晴海フラッグで起きた転売実態
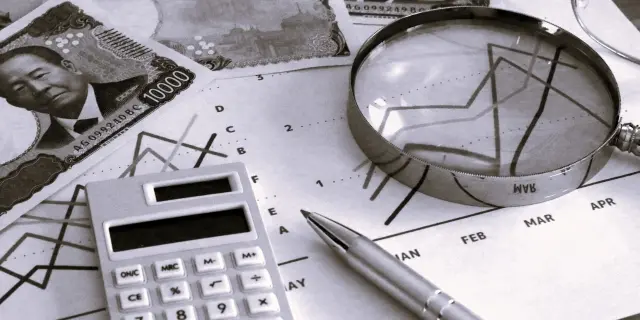
ここで、晴海フラッグ(HARUMI FLAG)という具体例が非常に示唆的です。
✓法人・業者による大量取得
晴海フラッグでは、法人名義での取得がかなり目立っているという報道があります。日刊ゲンダイによれば、1089戸を調べたうち、292戸以上が法人名義で購入されており、棟によっては法人所有が住戸の4割を占めるケースもあったといいます。
✓大手投資会社による爆買い
ある投資会社(福岡本社)は38戸を一社で取得したという報道もあります。
✓転売価格の急上昇
転売価格は発売時の2倍を超える例も指摘されており、坪単価で500万円以上という高値になる住戸もあるとの報道が出ています。〔朝日新聞〕
✓転売対策への対応
こうした事情を受け、事業者側(分譲元)は1名義あたりの購入制限(たとえばタワーマンションで2戸まで)を設けるなどの対策を取っています。
✓市場からの批判
ジャーナリストなどからは、晴海フラッグが「マネーゲームの舞台」と化しているとの声も。税金を投下されたオリンピック跡地である都有地やオリンピック村となった建物が割安で払い下げられた点を指摘する報道もあります。
✓居住実態の懸念
入居後、一部住戸では明かりが少ないという現状や、不動産業者が「転売希望者向け」に看板を建てているという報道もあり、実際の居住よりも転売・賃貸を目的とした購入が目立つとの指摘もあります。
これらは、「単なる投資用ではなく、短期的な利ざやを狙った投機目的の取得」がかなり現実に行われていることを示す重要な事例です。
3.なぜ「引き渡し前転売禁止」が重要なのか

晴海フラッグのような事例を見ると、不動産業界団体が今回打ち出した「引き渡し前転売禁止」の方針の意義がより明確になります。
というのも、引き渡し前の転売が認められない場合、購入者は実際に物件の引き渡しを受ける必要があり、その時点で物件価格の全額を資金調達しなければなりません。その結果、短期間での転売(いわゆるフリップ)は資金面・手続き面のハードルが高くなり、投機目的の取引を抑制する効果が期待できるためです。
-
- 過熱した転売を抑える
晴海フラッグでは実際に転売目的での購入が多発しており、これをコントロールする必要性がある。
- 過熱した転売を抑える
-
- 実需・長期保有層を保護
投機資金が増えると、本来住みたいファミリー層や将来の居住者が買えなくなるリスクがある。
- 実需・長期保有層を保護
- 市場の健全化
短期転売を抑えることで、価格の急変リスクを軽減し、投資というよりも住宅街としての価値を取り戻す可能性がある。
4. 投資家が受ける影響とリスクの変化
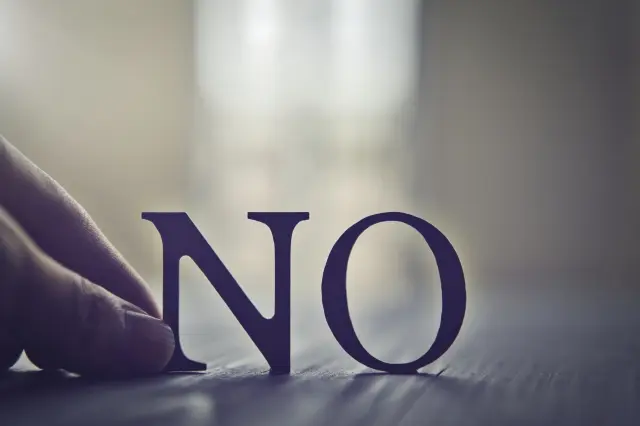
晴海フラッグのような極端な事例がある中で、「転売禁止」の方針が実際に導入されれば、以下のような影響が予想されます。
短期回転投資スキームが難化
完成前や引き渡し前に取得してすぐ売る、という戦略が取りづらくなる。
長期保有・賃貸運用の価値が高まる
転売目的の参入が減れば、賃貸需要を見込んだ保有戦略がより理にかなってくる。
契約条件の精査が重要に
転売禁止の条項、自社名義制限、ペナルティ条項などが契約書に盛り込まれる可能性があるので、これらを投資判断時に慎重に見る必要がある。
価格の変動リスクの低減
投機が抑えられることで、価格高騰・下落の振れ幅が小さくなる可能性がある。
5. 投資家が今押さえるべきポイント

-
- 契約内容の精査
転売禁止条項があるか等、違反リスクを含めて契約締結前に確認が必須。
- 契約内容の精査
-
- 保有目的の明確化
短期転売ではなく、賃貸や長期保有を前提とした投資戦略に軸足を置く。
- 保有目的の明確化
- 出口戦略の多様化
転売以外の選択肢(賃貸運用、中古市場での売却など)をあらかじめ想定。 - 市場・規制のモニタリング
今回のような転売抑制策の他にも、行政・業界からの規制強化の可能性を常にウォッチ。
6. まとめ:今後の不動産投資戦略

晴海フラッグでの大規模転売は、現代の都心不動産市場が「投機マネー」で加熱しやすいことを如実に示した事例です。
業界団体の「引き渡し前転売禁止」方針は、こうした過熱を抑え、実需や長期運用を重視する市場への転換を狙ったものと言えます。
これから不動産投資を行う際には、
- 短期売買を前提にする戦略ではリスクが高まる
- 長期保有+賃貸運用を軸に置くほうが有利な可能性がある
- 契約条項・出口・市場環境を慎重に見極める必要がある
という視点が、これまで以上に重要になります。



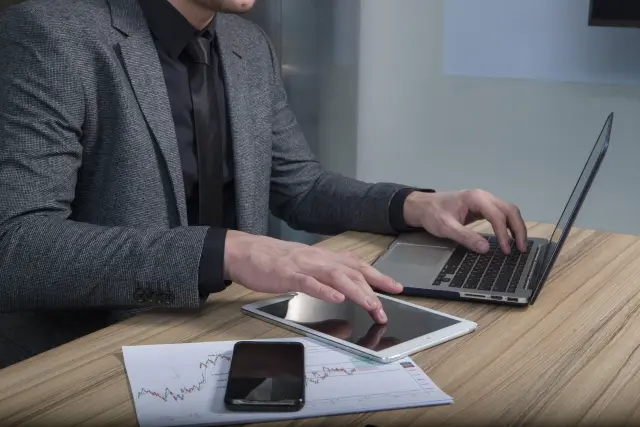
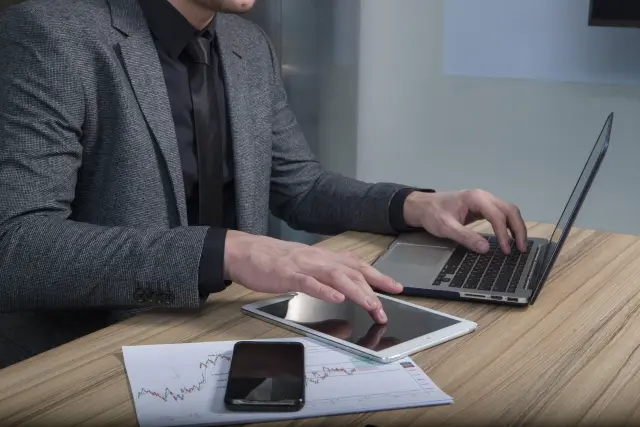




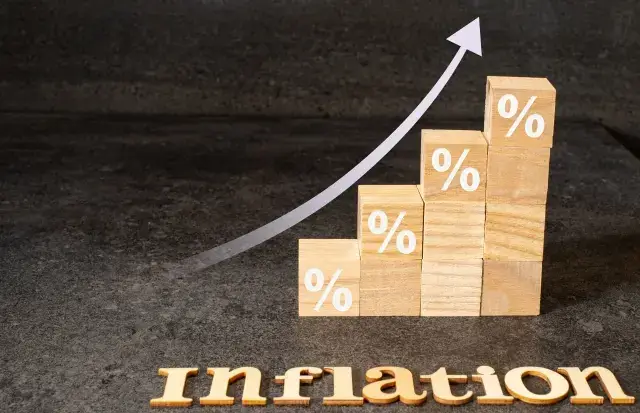
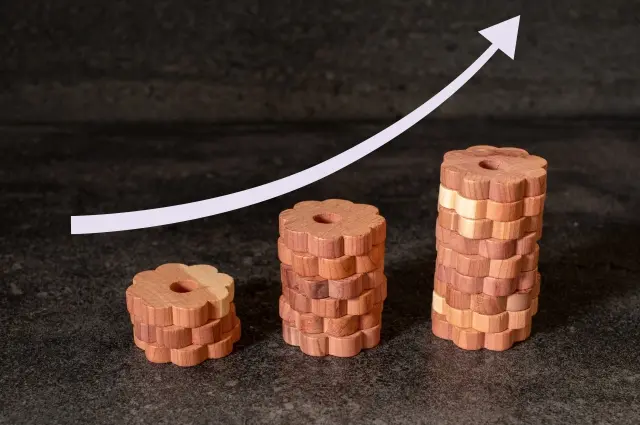
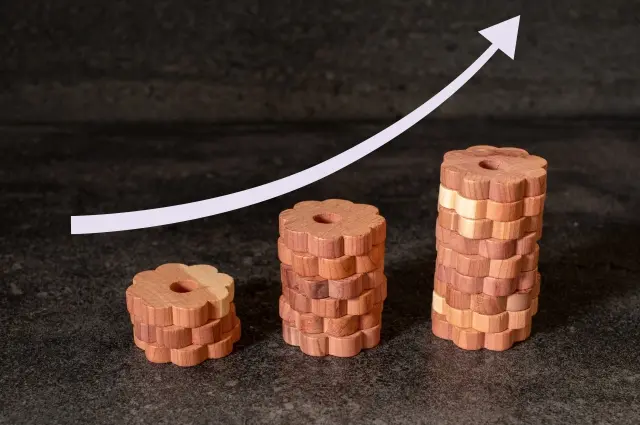 (※本記事は2025年3月31日作成、2025年12月12日更新)
(※本記事は2025年3月31日作成、2025年12月12日更新)
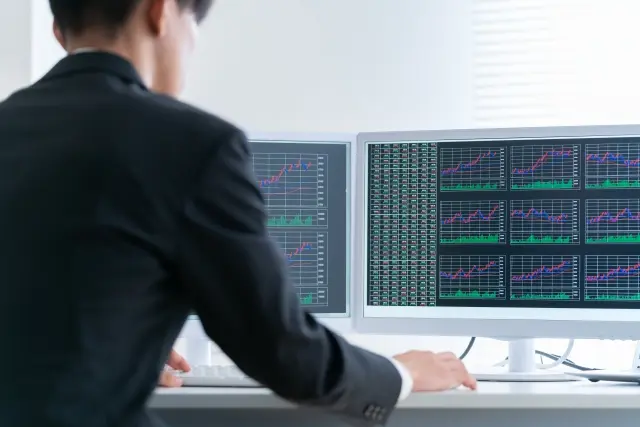




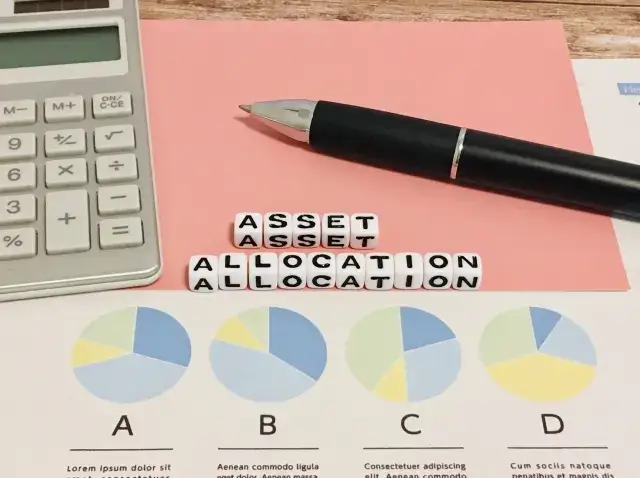

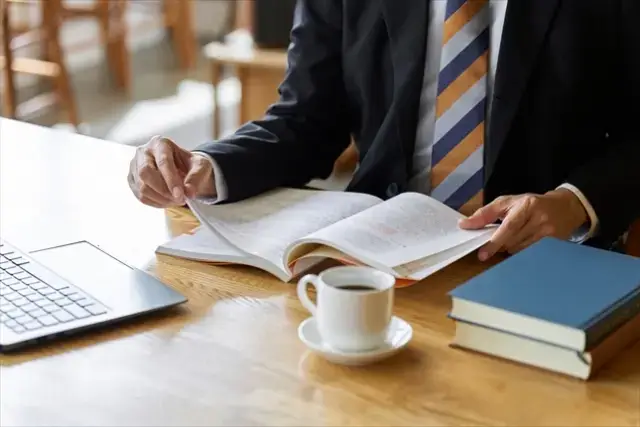
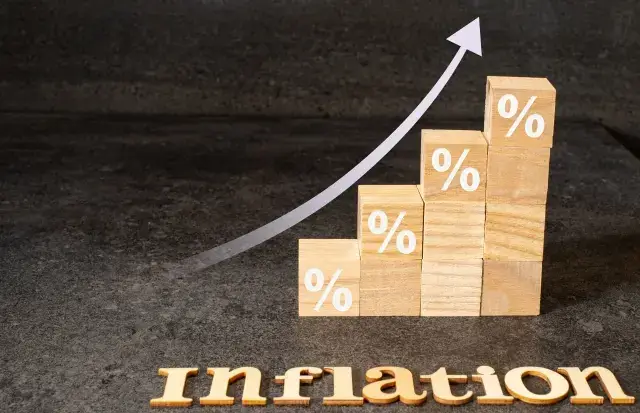

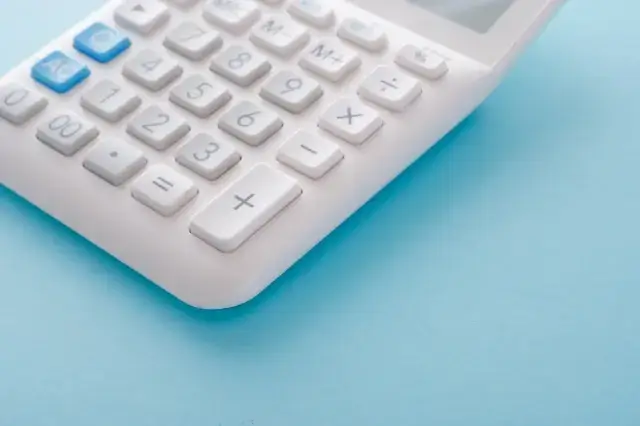



 (※本記事は2024年11月6日作成、2025年12月12日更新)
(※本記事は2024年11月6日作成、2025年12月12日更新)


